ドッグラン(というか犬のトイレ)として使っている我が家の庭ですが、フェンスの下の部分がワイヤーフェンスになっており、犬が足をかけられる構造だったため、脱走しないように壁をDIYで強化してみました。
絶対安全ということはありませんが、かなり脱走しづらい庭になったと思います。
もともと以下のような柵を作っていました。
下部はメッシュフェンスなのですが、隣の家の敷地のものなので手を加えることができず、その上に横方向に1×4材を取り付けてフェンスにしていました。
この方法だと、
- 下のフェンスに足をかけて上って逃げる
- メッシュフェンスと木の柵の間の隙間から逃げる(実際ここから逃げた)
- 高さが170cm程度しかなく心配
という欠点がありました。
そこで、犬が逸走する可能性を徹底的に排除するために、大がかりなリニューアルを実施しました。
犬が逃げづらいドッグラン用のフェンスとは
犬の運動能力は極めて高く、1メートルちょっとの壁なんぞ助走無しで乗り越えてしまいます。

これは以前滞在していたポインターですが、助走なしでこれくらい飛び上がります。
しかも、この写真はまだ飛び上がっている最中で、実際にはもっと上まで飛んでいます…。ということで、1mどころか、1.5m程度の柵なんぞ、中~大型犬にとっては無いに等しいことがわかるかと思います。
また、メッシュフェンスはたわみやすく、犬が頭を入れられる隙間があるとそこからフェンスをこじ開けて脱走します。
今までの柵は、メッシュフェンスが我が家のものではなかったために上部の木の柵と接合することができなかったため、わずかな隙間をよじ登って、メッシュフェンスの隙間から犬が脱走してしまいました。
メッシュフェンスの欠点はほかにもあり、それは足をかけられる、という点。フェンスをよじ登って逃げる犬もいるんですよね。
ですので、メッシュフェンスをドッグランのフェンスとして使うのはお勧めしません。
犬が逃げづらいフェンスとは、縦格子で足をかけるところがなく、高さはできれば2m、最低でも1.8mという条件になります。(あくまでも私の感覚によります)
業者に頼むと10mあたり70~100万円
縦格子で高さ2mという条件に合致するフェンスをエクステリア業者に施工してもらうと、エクスショップで計算したところ、10mあたり70~100万円となります。

私の家では施工する場所の長さが約50mですので、ざっと見積もっても350~500万くらいの金額になります。さらにドアが3箇所あるので、1カ所50万円とすると上記に150万円が加算されるので、安くても500万というとんでもない金額に…
さすがにその金額は出せませんので、安価に済ませるためにDIYすることにしました。
柵をDIYするのに最適な木材を探す
DIYするにあたり、どのようなフェンスにするか決める必要があります。
板を縦貼りする、縦格子フェンスにすることは決まっていますが、問題は木材をどうするか、という点。
2×4材で使われるホワイトウッドはお勧めできない理由
入手しやすいのは1×4材ですが、ウッドショック以降価格が上がっているのと、なにより耐久性のなさがネックです。

上の写真は、施工後5年くらい経った1×4材ですが、ひび割れが凄く、カサカサになっています。
ヒビから雨がしみこみ、気温差などでさらに割れが広がるという悪循環になって、あっという間に駄目になります。
数年に一度保護塗料で塗り直すと寿命を延ばせますが、塗装作業もそれなりの重労働になるので、メンテナンスを考えるとホワイトウッドはフェンス材としてはあまりお勧めできません。
耐久性30年以上を誇る最強の木材、ウリン
いろいろ探した結果、木材の中では最大の耐久年数30年以上を誇る、ウリン材を使用することにしました。ウリンはハードウッドの中でも耐久年数が高く、また、ポリフェノールを多く含むため防虫性に強く腐りにくいというメリットがあります。

ウリンのメリット・デメリットは以下となります。
メリット
- 非常に硬く、駆逐やシロアリの虫害に強い
- 雨や紫外線にも強く、30年以上という驚異的な耐久性
- 防腐剤などの塗装不要でメンテナンスが容易
- 硬度が高いため耐久性があり歪みづらく、薄い板でも十分な強度がある
- 赤褐色で深みのある色調と美しい木目
デメリット
- 希少性が高く、優れた特性を有するため価格が高い
- 非常に硬い木材のため加工がむずかしい(木ネジがちぎれる)
- とにかく重たい
- 施工して数ヶ月はポリフェノールが染み出てコンクリート等が染まることも
まず、メリットからみていきたいと思います。
耐久性が高く、とにかく腐りづらく、虫害にも強いこともあり、防腐剤などの塗装が不要というのはメンテナンスが少なくて済む上に、施工時にいちいち着色する手間が省けるのでとてもメリットが高いです。
施工前に着色→乾燥させるのはかなり手間がかかる上、切断した場合は切断面も塗り直す必要があるなど、とにかく面倒です。塗装不要というのは施工期間短縮というメリットも大きいです。
また、とても硬い木材ですので、水に濡れたりしてもゆがみがとても少ないです。
実際、400枚程度施工しましたが、雨に当たって明らかにゆがみが出たのはわずか2枚しかありません。
ホワイトウッドだとかなり反ったり割れたりしますので、ウリンの圧倒的な強靱さがわかります。
今回使用したのは12mm厚と薄めの板ですが、強度も十分です。
デメリットについてですが、やはりコストが高い、というのはあります。
今回は木工ランドというサイトで購入したのですが、2mまでは短尺特価となっており、割安になっているのでお勧めです。
厚み12mm×幅100mm×長さ1800mmのウリン材が1枚1,110円(送料別)で購入できますので、1×4の板を塗装する手間やその後のメンテナンスを考えると、高価とは思いません。

注意すべきは木ネジが使えない点で、そのまま木ネジを打ち込むと途中で木ネジがねじ切れます。釘も打てませんので、施工時は下穴を開けた上で木ネジで固定する必要があります。
下穴を開けるときに便利なのが、皿取錐というドリルビットです。木ネジ用の下穴と、皿ネジのビス頭部分の皿取り加工を1本で行える優れものです。
これは絶対に購入しておく方が良いです。
重量があるのもデメリット…というか、ハードウッドなので仕方が無い点ですが、2m尺の板だと1枚で2.3kgありますから、100枚買うと230kgになる訳で…届いた時の荷下ろしがかなり大変です。
どれくらい重たいかというと、ウリンは水に浮きません。

水につけるとこんな感じで沈んだままです。
それだけ密度が高く、硬い木ということです。
ウリン材を使ってフェンスを施工する
注文したウリン材が届いたので、早速施工していきます。
以前使っていたフェンスの支柱がそのまま使えますので、6cmの角材を横桟として渡し、そこにウリンの板を貼っていくこととしました。
2mの板であれば横桟は3本あったほうが理想なのですが、ウリンはあまり反ったりしないので、2本にして取り付けています。
フェンスの高さですが、1800mmの板をフェンス下部に20cm弱の隙間を空けて取り付けることで、2mを確保しました。下の方はオシッコされたりしますし、雑草を刈り取る際に少し空いていた方が工具を使いやすいので、少し隙間を作っておいた方がよさそうです。
下の隙間から犬が逃げないように、内側には1×4の板を水平に取り付け、隙間を塞いでいます。

板と板の間は2cm空けることとしました。1cmだと狭く、風圧をもろに受けてしまうことと必要な枚数が多いので金額が上がります。3cmだと思ったより隙間が広かったため、2cmに決定しました。
施工の際は、横桟に引っかけられるケージを自作して、等間隔になるようにしました。時々水平器を使って板が垂直になっているか確認しながら作業を進めると綺麗に仕上がります。

木工ランドで販売されている板ですが、長さが+1~3cm程度の誤差があります。そのため、下穴を開ける位置は板の上部から測る必要があります。
板の高さをそろえるには、水糸を張っておくのが一番簡単です。
水糸にあわせて板の高さを調整し、板の長さの誤差は下側にはみだすことで吸収することにしました。

家の裏側に繋がる通路には、犬が行かないようにドアを取り付け、さらにウリン板を貼って仕上げました。
ドアにフェンス材を取り付ける際は、ドリルネジを使うとネジがアルミフレームに穴を開けてくれますので作業が楽です。
この場所については、ドアの取り付けと支柱のみ業者に依頼し、横桟およびウリン板の取り付けはDIYで対応しました。

ドアは高さ1m程度のものでしたので、アルミのアングルを使用して上に伸ばし、ウリン板を取り付けました。
かなりドアの重量が増してしまったので、ヒンジ部分にかかる負荷が増えてましたが、今のところ問題はありません。
ここの場所、板の隙間が等間隔になるように何度も計算して全体の板の取り付け位置を決めていますので、かなり大変でした。
右側の板の高さが違うのは、ウッドデッキ分床が高くなっているため、その分フェンスも高くしているためです。
仕上がったフェンス

水糸で水平を確認しつつ、水平器で適宜板の角度を確認しながら施工したので、このような感じで高さもぴったり揃いました。
横から見ると、ウリン板に反りがないのが分かるかと思います。
1×4の板はかなり反っているものも多いので、このように綺麗にピシッと揃えるのは大変です。

街頭のポールが中央にあるので、ポールの左右から板を取り付けていきました。そうすることで、ポールの位置で板を切断することなく、見た目良く施工することが可能です。
メッシュフェンスから板張りに変えたことで、外の風景が見えづらくなり、庭にいる犬が外を散歩している犬などを見て吠えることが少なくなりました。

板を計算より5%ほど多めに購入したのですが、思ったよりも余ったこともあり、ボロボロだったDIYで作ったテーブルをリメイクしてみました。
木材も再度塗料で塗装しましたので、いい感じに仕上がったと思います。
施工に必要な工具・金具など
まずは工具から。
私はマキタの18Vシリーズで揃えていますので、マキタの製品でご紹介。
インパクトは必須です。ドリルでの穴開けも行いますので、18Vのハイパワーモデルをおすすめします。
コードレスの方が作業効率が圧倒的に上がりますので、買うならコードレス一択です。
丸鋸ですが、私は18VのHS631DZSというモデルを使っていますが、終売?なのかAmazonで見当たらず。なので、100Vモデルを貼っておきます。
横桟に60mmの角材を使っていますので、切込66mmの丸鋸であれば一発で切断できて重宝します。165mm径のチップソーを備えた丸鋸でも、切込57mmというモデルも多いので、購入する際は最大切込厚に注意すると良いかと思います。
ハードウッドのウリンですが、数枚重ねても18Vのバッテリー丸鋸で切断可能です。
ただし、厚さ50mmのハードウッドの角材を縦に半分にしようと思ったところ歯が立たなかったので、ハードウッドの角材には18Vバッテリーモデルは非力です。
京セラのエントリーモデルの100V丸鋸を使ったところ綺麗に切断できましたので、大トルクが必要なハードウッドの角材を切断するには、100Vの方が有利ですね。
ただ、取り回しの良さと、ケーブルを巻き込んで切断するリスクが無いのはバッテリーモデルのメリットです。
置き場所とお金の問題が無ければ、両方持っておくと一番良いかと思います。
板を貼る際に垂直になっているか、横桟を取り付けたり、水糸を張る際に水平になっているか…というように、垂直・水平を測ることが多々ありますので、水平器は必須です。
長さも様々ですが、木材は多少凹凸などがありますので、最低でも60cmくらいの長さは必要です。
板を直角に切断する際に重宝するのがスコヤです。
線を書く際の定規のように使うのも便利ですが、一番便利なのは、丸鋸を当てて切断する際のガイドとして使う方法です。
スコヤに沿って丸鋸をスライドさせれば、ぶれずに綺麗に直角に切断が可能です。
斜め45度の角度で切断する際も、スコヤに沿って丸鋸をスライドさせれば、ぴったり45度で綺麗に切断できます。
ドアに板を貼る際に使うアルミアングルを切断したり、ウリン板の切断面の面取りをしたりする際に必要になるのがディスクグラインダです。
研磨用ディスクは1枚付属しますので、別途、金属切断用ディスクを購入しておくと良いかと思います。
続いて金具についてご紹介です。
上でも説明したこちらの面取錐は必須です。
500枚程度の板であれば交換用のドリルは不要ですが、折れたりした場合のことを考え、1本スペアを買っておくと良いかと思います。

こんな感じで、皿ネジの頭が隠れるサイズの面取と、ドリルでの下穴開けが同時に可能です。
ウリン板を取り付けるのに便利なのが、コーススレッドです。
コーススレッドは木ネジと比べるとネジ山が深く、間隔が広い設計になっているため、木材にしっかりと食い込むことで強力な保持力を発揮できるネジです。
さらに、ネジ山が粗い(ピッチが広い)ために木ネジよりも打ち込む時間が短く、軸が細いので木割れが起こりづらいというメリットもあります。
コーススレッドの中でも細身のスリムビスというものがあるのですが、面取錐のドリルに適合するのは呼び径3.8mmのコーススレッドで、スリムビスだと細すぎてネジ山が木に噛まないので注意してください。
アルミの柱などに板を貼る際には、ドリルビスを使うのが簡単です。
ドリルビスはビスの先端がその名の通りドリル状になっており、下穴が不要でそのままネジ留めが可能です。
アルミのドアにはこのドリルビスを使って板を固定しています。
費用について
約50m弱を施工しましたが、
| ウリン板 | 500,000円 |
| 横桟用60mm角材 | 50,000円 |
| ドアおよび支柱施工(業者) | 480,000円 |
| その他雑費(ネジや金具など) | 50,000円 |
| 合計 | 1,080,000円 |
という結果となりました。
ドアは業者に施工を頼んだのと、ドア自体が高かったのでそこそこ金額がいってしまいましたが、他の部材がかなり安く済んだので、全て業者に頼むのと比べると圧倒的な低価格でフェンスを作ることができました。
手間はかかってしまいますが、見た目も良いですし、DIYで作ったものって愛着も出ますので、時間が確保できる場合はDIYでフェンスを作るのはお勧めです。
あとは、ウリン板がどれくらい持つか…というのと、柱と横桟が杉材なので、こちらのメンテを忘れないように気をつけないとです。



















































![ダイドーハント (DAIDOHANT) コーススレッド BK (呼び径d) 3.8 x (長さL1) 45mm (ラッパ / 全ネジ ) [鉄/ リン酸亜鉛] (500本入) 45762](https://m.media-amazon.com/images/I/21fSQaFLdFL._SL160_.jpg)





















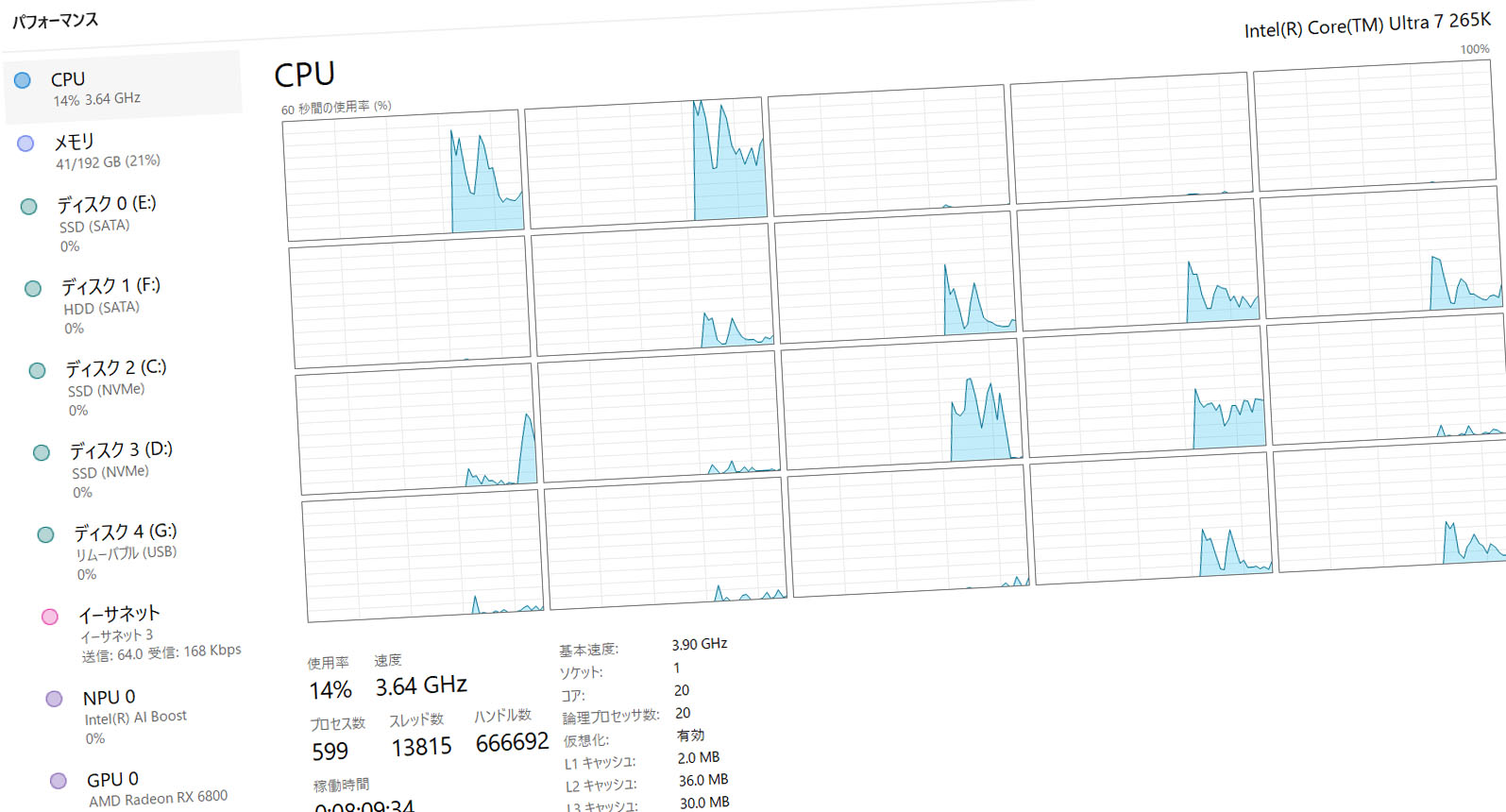

コメント